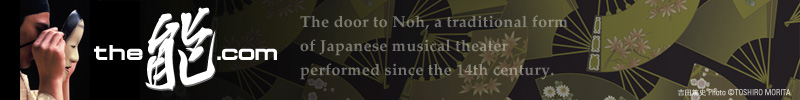
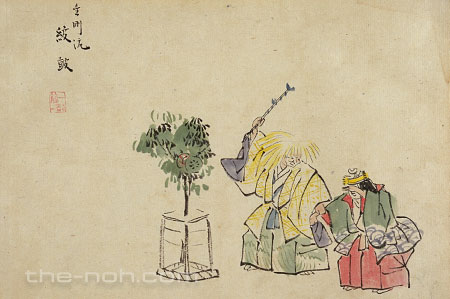
![]()
舞台は筑前の国、天智天皇の行在所の木の丸御所にある桂の池です。御所の庭掃きの老人は、とある女御を見て恋慕の情を抱きます。臣下は、池にある桂の木の枝にかけた鼓の音が聞こえたら姿を見せようという女御の言葉を、従者を通して老人に伝えます。老人は懸命に鼓を打ち続けますが、綾を張ったその鼓が鳴ることはありません。老人は悲嘆にくれて、池にその身を沈めます。
臣下は、従者に老人が入水したことを聞き、女御にそのことを伝えます。池の方から鼓の音が聞こえるという女御は、正気ではない様子となります。
そこに、池の底から老人の亡霊が現われ、鬼のような姿で女御を責め立てます。鞭を振って、女御に鼓を鳴らすように命じますが、鼓が鳴ることはありません。亡霊は因果の報いを思い知らせると、恨みの言葉を最後まで語りながら、池の淵へと消えていきます。
![]()
本作は、老人の恋の悲劇や怨恨が中心に描かれています。恋は年齢や身分に関係ないものですが、下賤な身の老人が、高貴な美女に恋をするという設定において、はじめから悲劇的な結末が予感されます。
前場では老人の一途な恋が描かれますが、後場では一転して、女御に弄ばれていたと感じた老人が恨みを強く持ち、女御を強く責め立てます。一方で女御の方も、綾でできた鼓を渡した時点で正気ではなかったと語り、この悲劇のやり場のなさが強調されます。最後の場面で再び淵へと消えていった老人の亡霊の行方も語られないままで、多様な解釈が可能となっています。
もともと「綾鼓」は宝生流と金剛流にありました。喜多流の「綾鼓」は、一九五二年に宝生流から贈られたものをもとに、歌人としても有名な土岐善麿と十五世宗家の喜多実によって大幅に改訂されたものです。「綾鼓」の類曲には「恋重荷」があり、観世流と金春流で上演されています。また三島由紀夫は「綾鼓」をもとに「綾の鼓」という戯曲を作り、法律事務所に小間使として勤める老人が洋装店の客の女性に恋をするという設定で、現代版に大胆にアレンジしました。現代だからこそ訴えかけるテーマも本作にはあると言えるでしょう。
▼ 演目STORY PAPER:綾鼓
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
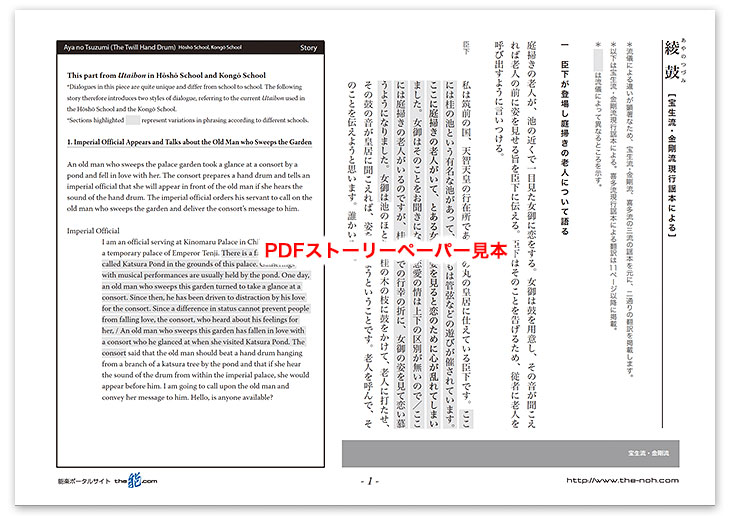
『解註・謡曲全集(第4巻)』野上豊一郎 著 中央公論社
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
『能楽手帖』権藤芳一著 駸々堂
『新編日本古典文学全集(59)』小山弘志・佐藤喜久雄・佐藤健一郎 校注・訳 小学館
各流謡本
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。
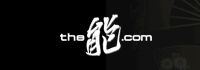


 [ 綾鼓:ストーリーPDF:585KB
[ 綾鼓:ストーリーPDF:585KB