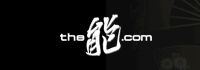 |
 |
 |
| > Top > 名人列伝 > 三須錦吾 |
|
|
三須錦吾(1832年〜1910年)
江戸時代の遺風を残す小鼓の名手
激しい修業で肋骨は歪(いびつ)になった
三須錦吾(みす・きんご)は明治時代に大活躍した幸流小鼓方の名手である。父、三須平左衛門は、加賀藩で幸流小鼓方を勤めた三須家の出で、江戸に上り、豊後竹田藩主の中川家に仕えていた。錦吾が生まれたのは1832年(天保3年)で、幼名を金之助といった。8歳の頃に小鼓の稽古を始めて以来、小鼓を持たない日はなかったと言われたほど、芸に打ち込んだ。そのためか、錦吾の肋骨はいびつに発育し、左の方が大きく隆起していたと伝えられている。
幼時より優れた素質を顕し、江戸末期の名人として名を馳せた幸五郎次郎にかわいがられ、11歳から13歳まで幸家に引き取られて実子同様の指導を受けた。初舞台は13歳の時、宝生流の田村の能で役を勤めた。以降、抜群の技量を身につけて、大役の舞台にも上がるようになる。幕末の混乱期より明治初期の能楽不遇の時代には、一時藩主に付き従い、豊後竹田(今の大分県竹田市)の地に身を置いた。1878年(明治11年)に再び上京すると、未だ危機を脱していなかった能楽界をよく支えて芸にますます磨きをかけ、各流儀の大事な演能に名を連ねた。関寺小町を2回(シテは梅若実、宝生九郎)、檜垣(シテは梅若実)姨捨(シテ観世鐵之丞)と、最難度と目される三老女の大役も都合四度勤めている。
明治能楽界を支えたシテ方の名人、宝生九郎は、太平に栄えていた幕末までの能楽社会を度々懐かしみ、明治から見れば夢のようだと語った。そして、こと三須錦吾については、往時のめくるめく囃子方の名手と比べても変わらない力を持つ、と評した。
質素に暮らし、技芸に打ち込み、後進を育む
三須錦吾本人は、ただただ技芸をのみ追求する、質実の人であった。明治の能楽危機の頃、貧しい暮らしを強いられることがあっても頓着せず、後年財を得られるようになっても昔と変わらず、恬淡として芸のみに励んだという。とはいえ吝嗇ではなく、平素は質素倹約に努めつつも、気に入ったものには糸目をつけずに財を投入して求める一面もあった。
芸を追求する姿勢はいささかも崩れなかった。門弟には厳しく接し、華族でも資産家でも手心は一切加えず、技量が足りなければ決して重い習い物を許さなかった。跡継ぎのわが子でも、足りないところがあれば誰が見ていようがかまわず厳しく叱責した。その一方で裕福でない市井の者でも熱意があり、技能に優れた門弟には、求められなくても自分から免状を与えた。彼の質朴さと芸の上での公平さは、接する人びとに自然な感銘を与えた。能楽界に関わる多くの人から尊敬され、求めることなく高名を得たのである。
1910年(明治43年)の夏、三須錦吾は肺炎により78年の生涯を閉じたが、彼を惜しむ声は引きもきらなかった。葬儀には蜂須賀、鍋島、細川の諸侯爵ほか多くの華族を含め300名を超える参列者があり、まことに稀有な盛儀であったと記録されている。
「小鼓の本質を体得した、消極的な趣」
三須錦吾は他の芸を見る力に優れ、門弟の育成にも定評があった。竹田でも後進の育成に努め、九州で小鼓をしっかり打てる人を幾人も育て、東京へ出てからも数多くの門弟に恵まれた。子の三須平司をしっかり導いて見事な後継者に鍛え上げ、幸流の至芸を絶やさぬようにした。さらに昭和の大名人となる幸祥光(幸悟郎)を見出したのはまさに慧眼といえよう。自分の家の門前を通って学校に通う児童のなかから、ひときわ唱歌の上手い子を見つけて平司の養子としたのだが、その子こそ後の幸祥光その人であった。
能楽研究家としても著名であった建築家の山崎楽堂によれば、その芸には「小鼓の本質を体得した受身なところ、消極的な趣」が特徴的であったという。楽堂は、押し出し強くやりすぎれば小鼓らしくなく、また定跡通りにやりすぎても芸術味に薄いと感じており、小鼓を打つ多くの者がそのいずれかになってしまう、と断じている。ところが三須錦吾は、自分は目立たずに、他の囃子、シテ方との調和による最高レベルの演奏を引き出すことにかけて卓抜な手腕を発揮したという。楽堂自身が大鼓を学び、三須と一緒に打った経験を持っていたゆえに、その感想は、三須錦吾の芸風を今に伝える生きた証言といえるだろう。
【参考文献】
- 『能楽』1〜12 池内信嘉 編(第一書房)
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.