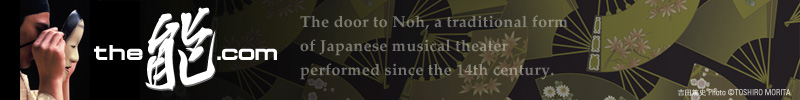
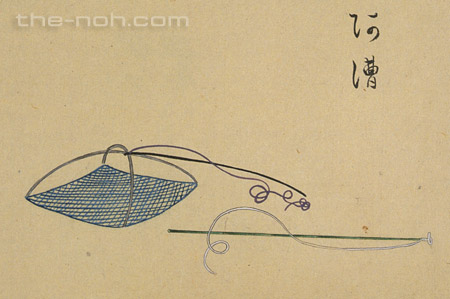
![]()
九州日向国の旅の僧と従僧(または日向国の人)が、伊勢神宮参詣の旅に出ます。途中、阿漕が浦(今の三重県津市阿漕町あたりの海岸)に着きます。旅僧一行(旅人)は、そこで一人の老いた漁師に出会います。老人は旅僧たち(旅人)と阿漕が浦にまつわる古歌について語り合います。旅僧(旅人)が、阿漕が浦の名前にどんな謂れがあるのかと尋ねると、老人は、昔、阿漕という漁師が禁漁区で魚を取り、見つかってこの裏の沖に沈められたことを伝えます。そして、阿漕の霊は罪の深さにより、地獄で苦しんでいる、弔いをなされよ、と語り、自分がその亡霊であることをほのめかし、急に吹いてきた疾風のなか、波間に消えていきました。
近隣の里人から改めて、阿漕の最期を聞いた旅僧たち(旅人)は、法華経を読んで阿漕の跡を弔います。すると夜半に阿漕の霊が現れ、密漁の様子を見せ、さらに地獄の責め苦にあう自らの惨状を示します。行き場のない苦しみを訴えながら、阿漕は「助けてくれ、旅人よ」と言って、波の底へ入っていくのでした。
![]()
禁漁を破った漁師の悲惨な死と、その罪業により死後もなお苦しむ姿を、緩急鋭い謡や囃子、抑制された型を伴う、能の研ぎ澄まされた表現により、静かに、そしてたとえようもなく恐ろしく描き出した曲です。
阿漕が浦は昔、伊勢神宮に供える魚のみを取るよう決められた禁漁区でした。ところが、夜中に忍んで、魚を取る漁師がいました。何度も密漁した彼の行為は露見し、捕えられ、処罰されました。古来、そのような伝説が伝わり、その伝説を下敷きに歌も詠まれ、歌をもとに能ができたと考えられています。その歌は能のなかに出てきます。
前半では、僧と漁師の会話を中心に静かに進行しますが、突然に急転して中入りし、後半は漁師の亡霊が出て、逃げ場のない恐ろしい地獄の有様を見せます。最後は「助けてくれ」と声を上げながら海に消えるという、救いのないかたちで終わり、凄惨さが心に深く刻まれます。
ワキは旅僧ですが、観世流では旅僧としてよりも、旅人として登場するのが普通です。
ところで日本語には「あこぎ」という言葉がありますが、この能でも取り上げられる伝説や和歌をもとに、昔は「度重なれば露見する」といった意味で使われていました。このことは、能の中でも触れられています。ところが後に、「あこぎ」という言葉には「無慈悲な、人情のない、ひどい」「ずうずうしく、しつこい」「浅ましく、金品をむさぼる」といった意味が加わり、現在では主に、こちらの意味で使われるようになりました。
▼ 演目STORY PAPER:阿漕
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
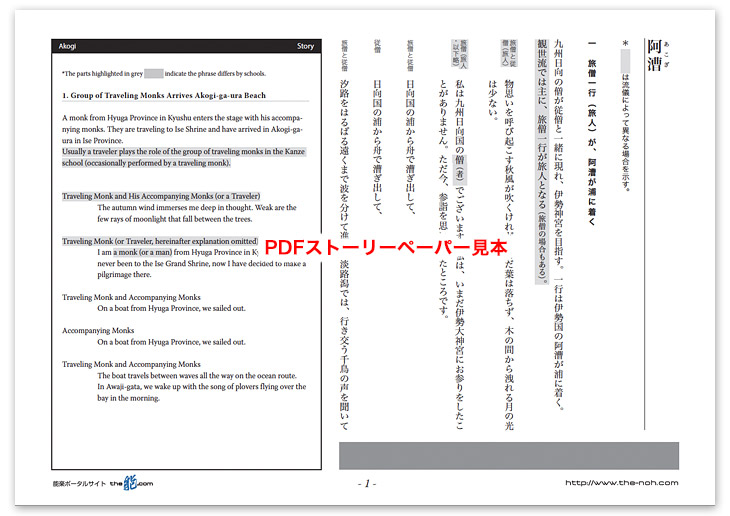
『能楽手帖』権藤芳一 著 駸々堂
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
各流謡本
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。
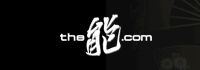


 [ 阿漕:ストーリーPDF:445KB
[ 阿漕:ストーリーPDF:445KB